
なぜ銀行に置かないのか?
日本人は「貯金が安心」という意識がとても強く、統計でも個人金融資産の半分以上が現金・預金に偏っています。
実際、銀行に数百万円単位で眠らせている人も多いのではないでしょうか。
でも現実はどうでしょう?
普通預金の金利は0.001%ほど。100万円を1年間預けても、増えるのはわずか10円。
定期預金にしても0.2%前後で、100万円預けてようやく年間2,000円。



僕が特定口座でオルカンを選んだ理由
投資を続けていると必ず出てくるのが「NISAを埋めたあとのお金をどうするか」という問題。
我が家では夫婦で新NISA積立投資枠を満額(月10万円×2人分)使っていますが、それでもボーナスや臨時収入が入ると「NISAにはもう入れられない」という状況になります。
選択肢は3つ。
- 銀行に置いておく
- 定期預金に回す
- 特定口座で投資する
銀行や定期に置けば「減らない安心感」はありますが、増えるスピードはほぼゼロ。
一方、オルカンは世界中の株式に分散投資できる王道ファンド。信託報酬も低く、長期で年数%の成長を狙える。
だから僕は「余剰資金は特定口座でもオルカン」というシンプルな結論にたどり着きました。
実際にどうなったか(運用結果)
2025年8月時点でのオルカン評価額は24,574,971円(損益+440万円ほど)。
この中には、特定口座での追加投資も含まれています。
もし銀行に置いていたら、得られた利息はせいぜい数千円。
でも投資に回したことで数百万円の利益を得られました。これが「銀行に置かず運用した結果」です。
さらに大きいのは心理的な効果でした。
銀行口座にお金があると「ちょっと大きな買い物してもいいかな」と手を出したくなる。
でも証券口座に移した瞬間、そのお金は「長期投資用」だと自然に意識できるようになり、生活資金とは切り離せます。
そしてもう一つ大事なのが、暴落時の気持ちです。
例えば一時的に評価額が▲20%下がったとき、銀行に置いていれば「減らなくてよかった」と安心できたかもしれません。
でも僕は「銀行に置いていたら、この先の回復や成長は得られない」と思うようにしています。
実際、過去に相場が下落しても数カ月~1年で戻る場面を経験しました。あのとき銀行に置いていたら、ただ指をくわえて眺めるしかなかったはずです。



この感覚に変わってからは、特定口座でも迷わず投資に回せるようになりました。
特定口座で投資するときの注意点
もちろんデメリットもあります。
- 売却益には20%超の税金(所得税+住民税)がかかる
- 配当金にも課税(オルカンは配当が少ないので影響は軽微)
- 利益が大きくなれば住民税や社会保険料に影響する可能性もある
この「課税」をデメリットと捉える人は多いと思います。僕も最初はそうでした。
でも、冷静に考えると「税金がかかる=利益が出た証拠」です。銀行に置いておけば課税もされませんが、利益もゼロ。
また「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおけば、基本的に確定申告は不要。サラリーマンでも手間なく投資できます。
僕は「税金=投資がうまくいった証拠」と考えるようにしています。そう思えると、むしろポジティブに受け止められるようになりました。
まとめ:銀行に置くより投資に回す方がいい
僕の結論は変わりません。
「余剰資金を銀行に眠らせるくらいなら、特定口座でもオルカンに投資する」。
もちろんNISA優先は大前提ですが、それを埋め切ったあとにどうするかで将来の資産形成は大きく変わります。
実際に特定口座を活用したことで数百万円のリターンを得られただけでなく、心理的にも「投資用のお金」と生活資金をきっちり切り分けられるようになりました。
そして暴落時でさえ「銀行に置いておけば安心だった」とは考えなくなり、むしろ「投資を続けているからこそ回復を一緒に受け取れる」と思えるようになったのは大きな変化です。
銀行に置く安心感も大事ですが、“増えない安心”に甘えるより、“育ちながら課税される安心”の方が僕には価値がある。
これからも僕は、NISAと特定口座を使い分けて“銀行に眠らせない投資”を続けていきます。
関連記事として、オルカンに関する詳しい解説はこちらもどうぞ:









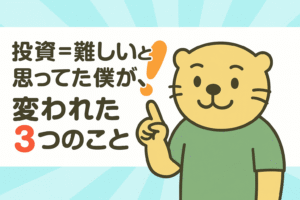

コメント